| 今週のおすすめ〔20〕 |
◇小津安二郎『麦秋』の紀子について (2008/04/04)  ◇今回も映画の話です。毎度映画の話をするつもりはないのですが、もう少しお付き合いいただければ幸いです。また、今回とり上げる『麦秋』も当店の目録にはありません。その点もご了承ください。 ◇今回も映画の話です。毎度映画の話をするつもりはないのですが、もう少しお付き合いいただければ幸いです。また、今回とり上げる『麦秋』も当店の目録にはありません。その点もご了承ください。◇前回申しましたように、小津安二郎の『麦秋』は昭和26年に公開された映画です。もっと細かくいうと昭和26年10月3日公開。私ごとを言わせていただくと、この映画が公開されたときにはもう生まれていました。映画をみてもなんにも分からないない赤ん坊でしたが。また、私は昭和30年以降の北鎌倉と鎌倉のことはよく知っています。ですからこの映画を初めてみたときは、原節子演ずるヒロイン紀子たちの家は鎌倉にあるらしいのに、北鎌倉駅から出勤していくのをみてびっくりしました。小津は観客に謎をかけているのかとも思いました。 ◇その出勤の場面に続くのが、北鎌倉駅を出ていく上り横須賀線を北鎌倉女子学園付近の高台に置いたと思われるキャメラで撮った超ロングショットです。しかし、そのショットも登場人物の視点とは関係がないらしいことが分かってきます。いずれにしても、この映画の導入部にはちょいと驚かされます。紀子たちの父・間宮周吉を演じた菅井一郎も、自分たちの家が鎌倉のどこにあるのか分からなくなったと証言しています。 ◇もちろん、分からなくていいのです。旧鎌倉市街地に住むと思われる紀子たちを北鎌倉駅から出勤させているのは、ひとつは散文的な鎌倉駅では絵になりにくいこと。もうひとつは出勤していく紀子が二本柳寛演ずる矢部謙吉と駅で会う場面が必要とされたこと。このことはあとで意味を持ってくるのですが、鎌倉駅は通勤通学客が多いから、人の少ない北鎌倉駅にする必要があったということでしょう。『晩春』の父の場合は、普通の人より遅い時間に出勤しているようですから、鎌倉駅から電車に乗っていますが。 ◇そういうわけで、紀子たちの家の場所はどことは指定されておりません。しかし敢えて推測してみると、「お兄さん、急がないとあと7分よ」という紀子のセリフからして、駅(北鎌倉駅ではなく鎌倉駅と考えた方がいい)から急ぎ足で5、6分のところ。更に、画面に出てくる由比ガ浜と長谷の大仏からそう遠くないところ。そうすると、御成町、由比ガ浜、佐助、笹目町のあたりということになります。もう少し範囲を広げると、長谷、小町、扇ガ谷を入れてもいいかもしれません。映画では紀子が3歳の孫娘を連れた杉村春子演ずる矢部たみ(矢部謙吉の母)と長谷の大仏で偶然会うという設定になっていますから、たみたちの家もそのあたりと考えられます。紀子たちの家からたみたちの家は歩いてせいぜい10分程度と思われます。画面を見た感じからいえば、紀子たちの住む家の場所は長谷か笹目町とするのが妥当ではないかと思われます。 ◇この『麦秋』については、以前「KILLER MUSIC」ページの「管理人のつぶやき」で駄文を書いたことがあります(2006/04/06〜2006/05/18)。しかしその頃はまだ小津映画の全体像がつかめておりませんでした。従ってそのときとはアプローチの仕方も違ってきます。前回、フロイトによるナルシシズムの定義からすれば『麦秋』の紀子がナルシストの資格を十二分に備えていることは明らかですということを書きましたが、そういう方向から「『麦秋』の紀子とは誰か」ということを改めて考えてみたいわけです。 ◇そのような観点からこの映画をみていくと、紀子の結婚の決定はどのようにしてなされたか、ということが問題の中心になります。いやそもそもこの映画で語られているのはそのことです。つまり紀子とはいかなる人間であるかということ。父(菅井一郎)、母(東山千栄子)、兄(笠智衆)、兄嫁(三宅邦子)、そして紀子の甥に当たる兄夫婦の子供たちからなる家族との関係から始まり、父の兄に当たる大和からきた老人(高堂国典)、紀子が勤めている会社の専務(佐野周二)、親友のアヤ(淡島千景)、戦死した次兄省二の友人矢部謙吉(二本柳寛)、その母たみ(杉村春子)といった登場人物たちとの交渉のなかから紀子のキャラクターが立ち上がっていく。そして彼らの関心も紀子の結婚ということに集約されていく。その過程がこの映画の物語にほかならないわけですから、上に述べた「方向」なり「観点」なりは決して特殊なものではないことになります。もともとこの映画はそういう「方向」「観点」からつくられている。そう言って構わないわけです。 ◇この映画には紀子という人間のあり方を示唆する箇所があちこちに見られます。しかし、紀子の人格の核心にあるものが画面全体に溢れ出すのは、紀子が矢部謙吉と話をするニコライ堂が見える喫茶店の場面です。そこで二人は、スマトラ島あたりで戦没したと思われる紀子の次兄で、謙吉の同級生だった省二の話をします。紀子「よく喧嘩もしたけど、あたし、省兄さんとても好きだった」、謙吉「あ、省二君の手紙があるんですよ。徐州戦の時、向うから来た軍事郵便で、中に麦の穂が這入ってたんです」、紀子「ーー」、謙吉「その時分、僕はちょうど『麦と兵隊』を読んでて・・・」、紀子「その手紙、頂けない?」、謙吉「ああ、上げますよ、上げようと思ってたんだ」、紀子「ちょうだい。あ、来たわ(待っていた長兄の康一が)」。 ◇紀子の表情から何かが溢れ出すのは、謙吉から省二の手紙のことを聞いた直後です。手紙の話をする謙吉から紀子に切り返されたときの、それまでとは一変した表情に驚かされます。謙吉から再び紀子に切り返されたところで、「その手紙、頂けない?」となるのですが、謙吉も紀子の表情の変化に気圧されていることが分かります。「上げようと思ってたんだ」という弁解じみたセリフに謙吉の受けた驚きが聞かれます。「あ、来たわ」で元の紀子に戻るのですが、既に紀子を包む世界はステージが変わっています。これは同じ小津安二郎の『晩春』における、叔母から父の再婚話を聞いた直後の紀子の変化に対応しています。しかし『晩春』の紀子に現われるのは憤りですが、ここに現われるのはエロス的なものです。つまり、ここで紀子は自分自身のエロスを規定しているものに気づく。それが戦争で死んだ省二の存在(不在)だったわけです。 ◇この場面に続くのが謙吉の母たみが紀子にプロポーズする有名な場面ですが、そこで「あんたのような方に、謙吉のお嫁さんになって頂けたらどんなにいいだろうなんて、そんなこと考えたりしてね」という申し出を紀子が「素直に」受けるのは、自然な成り行きです。紀子の決定的な自己認識を媒介した当の人物こそ謙吉だったわけですから。それに「その手紙、頂けない?」、「ああ、上げますよ、上げようと思ってたんだ」というやりとりはもう済んでいます。しかし帰宅した謙吉はその話を聞いてやはり衝撃を受ける。謙吉の「嫁に?」には驚愕が現われている。たみは前日のやりとりを知らないから、「あたしゃ、お前がどんなに嬉しいだろうと思ってさ」と言いますが、謙吉は紀子の"秘密"を知ってしまったわけだから、嬉しさより事態を理解することに注意が向いている。しかし、たみに「嬉しいだろう?」と何度も聞かれれば、「嬉しいさ」と答える以外ありません。 ◇この映画の物語はここから終盤に向かっていくわけですが、紀子の決定を覆すことができる人間は誰もおりません。このことに関連してデヴィッド・ボードウェルは次のように述べています。「彼女(紀子)の罪は、今日の西洋の観客には明らかではないかも知れないが、甚だしいものである。彼女は(・・・)誰にも相談せずに決定して、自分の結婚相手を選ぶ権利を、家族にまったく与えない。(・・・)要するに、彼女は伝統を無視して行動するのである」(デヴィッド・ボードウェル『小津安二郎・映像の詩学』青土社P.516)。それはそうかもしれないが、紀子が戦前・戦中・戦後を貫く歴史の化身のような存在として描かれるかぎり、その決定は動かしようがありません。そういうことが緊密に描かれている以上、この映画は間違いなく名作と言えますが、そのことによって紀子が少し人間離れした存在になってしまったことは否定できないでしょう。 ◇しかし言うまでもなく原節子演ずる『麦秋』の紀子はこわいほど魅力的です。『晩春』と『東京物語』を併せた紀子3部作のなかでもとびきり魅力的なのがこの『麦秋』の紀子かもしれません。魅力的という意味はリアルという意味でもあります。しかし、そうであるが故にこの映画にはなにか謎めいたものが残ります。それは戦前・戦中・戦後を貫く歴史の謎であるとともに、戦後という時代が生み出そうとしていた謎であるとも受け取ることができます。「古風なアプレゲール」という言葉は、そのような謎を指示する言葉なのかもしれません。過去が問いかけてくるものは『麦秋』においてだけでなく、『東京物語』においても主題化されています。しかし"来たるべき謎"とでも言うべきものについては、小津自身もそれほど意識的ではなかったと思われます。しかしこの映画が私たちに問いかけているのは、むしろ"来たるべき謎"についてではないか。そのように考えないと、この映画の底にあるものは見えてこないのではないか。そう思われてなりません。 |
| 今週のおすすめ〔19〕 |
◇吉田喜重の8月15日映画『秋津温泉』 (2008/03/28)  ◇前回の最後のところで申し上げたように、吉田喜重の映画『秋津温泉』の岡田茉莉子演ずるヒロイン新子とは誰かという問いは、私たち自身の問いでもあります。その理由を、戦後の日本人は総じて「古風なアプレゲール」ですからと申しましたが、それはそう評される『麦秋』のヒロイン紀子(のりこ)が新子と同じ種類の人間であるという意味ではありません。『麦秋』の紀子にしたってナルシスシズムの傾きがありますが、紀子は新子ではありません。そもそも人間は大なり小なりナルシストです。それが新子の場合のように自分自身の滅びにつながることは稀であるとはいえ、そのような危険には普遍性がある。映画『秋津温泉』が私たちを震撼させる理由はそこにあります。 ◇前回の最後のところで申し上げたように、吉田喜重の映画『秋津温泉』の岡田茉莉子演ずるヒロイン新子とは誰かという問いは、私たち自身の問いでもあります。その理由を、戦後の日本人は総じて「古風なアプレゲール」ですからと申しましたが、それはそう評される『麦秋』のヒロイン紀子(のりこ)が新子と同じ種類の人間であるという意味ではありません。『麦秋』の紀子にしたってナルシスシズムの傾きがありますが、紀子は新子ではありません。そもそも人間は大なり小なりナルシストです。それが新子の場合のように自分自身の滅びにつながることは稀であるとはいえ、そのような危険には普遍性がある。映画『秋津温泉』が私たちを震撼させる理由はそこにあります。◇ここで引き合いに出した『麦秋』は1951年に公開された小津安二郎の映画です。そのヒロインが原節子演ずる紀子であるわけですが、彼女のナルシシズムは映画をみるかぎりではそれほど前景化されていません。しかし紀子が誰にも相談せず、結婚をひとりで決めたあとのさまざまな仕草にそれを見ることができます。それが言葉で語られるのは、笠智衆演ずる兄・康一による次のようなセリフです。「(12歳の頃の紀子は)こんなところへ、ちょこんとリボンなんかくっつけて、よく雨降りお月さまなんか歌っていましたよ。」 ◇ここに言われる「雨降りお月さま」とは、野口雨情作詩、中山晋平作曲による「雨降りお月」のことで、歌詞は次のようなものです。「雨降りお月さん、雲の陰/お嫁にゆくときゃ、誰とゆく/ひとりで傘(からかさ)、さしてゆく/傘ないときゃ、誰とゆく/シャラシャラ、シャンシャン、鈴つけた/お馬にゆられて、濡れてゆく」。これは大正14年に発表された歌ですが、紀子の独立不羈ぶり、彼女に特有の行動様式を見事に言い表わしています。更に紀子の女学校時分のアイドルがキャサリン・ヘプバーンであったという親友アヤ(淡島千景)のセリフを併せると、紀子のナルシシズムのあり方はいっそう明確になります。 ◇ところでその紀子が「古風なアプレゲール」と評されるのはなぜでしょうか?それは紀子が結婚を決めた相手の謙吉(二本柳寛)が、彼女が「好きだった」と言う次兄・省二の親友だったことからきています。その次兄はスマトラあたりで戦死したと考えられていますが、紀子は次兄に執着しています。謙吉はそのことを知っているから彼女が嫁にきてくれることを母親(杉村春子)のようには無邪気に喜べないのですが、ともかく紀子が戦前、戦中の継続としての戦後を生きる人間であることは明らかです。ここに過去を忘れつつある戦後日本とのずれが見られますが、独立不羈のナルシスト紀子の自己=歴史認識はそういうものです。 ◇そういう意味では『秋津温泉』のヒロイン新子も、『麦秋』の紀子とほぼ同じ志向の人間と言えます。しかし『秋津温泉』と『麦秋』とでは映画のテーマが違います。『麦秋』では戦後ということはそれほど強く前景化されませんが、『秋津温泉』では戦後そのものが主題化されます。それゆえ『秋津温泉』におけるヒロインの描き方は、『麦秋』のそれとはまったく異なります。『秋津温泉』では昭和20年8月15日におけるヒロイン新子の行動が決定的な意味をもちます。新子は女中のお民と食料の買い出しに行った帰りに玉音放送に接します。日本の敗戦を知った新子は秋津荘まで全力で走って帰り(この場面は木下恵介『二十四の瞳』からの引用かもしれません。吉田は木下の助監督としてスタートしていますから)、周作が休んでいる離れで大泣きに泣きます。秋津荘にきていた軍人の前で「日本は負ける」と口走った新子が「1時間も2時間も」泣くのです。 ◇新子が8月15日に大泣きに泣くことの意味は映画でははっきりとは語られません。しかしそれが新子の生命力の爆発であることは明らかです。日本の敗戦が新子にとっても耐えがたい苦痛であり悲しみであることはたしかだと思われますが、「1時間も2時間も」泣くことを通じて新子という人間の生が解放されます。周作と一緒に秋津の高原を散策する場面で、周作から離れた新子はいかにも気持ちよさそうに高原の空気を吸って、「ああいい気持ち。戦争って本当に終わったのね。嘘みたいだわ」と言う。秋の高原から見る広大な風景に向かって。そしてそこに溶け込んだ自分自身に向かって言うように。これが新子にとっての戦後の原風景であるようです。8月15日に大泣きに泣いた新子の目に見えてきた戦後日本の原風景。 ◇新子が自分自身を解放していくチャンスはそこにあったようにも思えますが、どうやらそうではなかったようです。なぜなら新子にとって8月15日と昭和20年夏の日々は周作とともにあったからです。新子にとって8月15日とは肺病で死にかかっている周作への献身的な看護と不可分であったからです。新子の生きることと愛はそういう形で解放されます。この映画における秋津は一種のサナトリウム空間として見ることができます。周作がそこに滞在する結核患者であるとすると、新子はサナトリウムの看護者ということになります。このように見ると、新子が秋津を離れない理由が見えてきます。周作がそれほどの後ろめたさもなく「おめおめと」新子のいる秋津にやってくる理由も分かってきます。もちろんこれはそうも解釈できるということですが、藤原審爾の原作を読めば、映画では分かりにくい含みが見えてくるかもしれません。 ◇この映画の終わりの方で、「一緒に死んで」と懇願する新子に対して周作は次のように答えます。「生きるとか死ぬとかってのはねえ、そんなことはもう昔のことなんだ」。更には「そりゃあ生きてたって意味はないかもしれないよ。だがね、だがそういうもんなんだよ、人間てのは」とも。このあとの方の言葉を聞いたあと新子はひとりで命を絶つことを決意します。当然の決定と言えます。新子にとって8月15日とそこから始まる戦後は「生きること」そのものだったからです。しかし周作は、意味がないかもしれない生、生きているのか死んでいるのか分からないような生も人間の生であると言う。これは新子にとっては「生きること」それ自体への侮辱であり、裏切りです。その周作の言葉に確固としたものが感じられないこと、しかも周作は折にふれて新子から「生きること」を教わったと語っていただけに、いっそう許しがたい裏切りと感じられる。 ◇そもそも戦後を生きる私たちにとって8月15日とはどういうものでしょうか?それについてこれまで多くの人たちがさまざまに語ってきたと思いますが、私がいちばん納得したのは昭和20年9月5日の朝日新聞社説から「8月15日正午の天籟」という言葉を引いている桶谷秀昭の文章です(桶谷秀昭『昭和精神史』文藝春秋)。「天籟」というのは『荘子』「斉物論」にある言葉だそうです。従って本当の意味はよく分かりません。とにかくそれは天地が裂けるような経験であったのですが、同時にある啓示でもあったらしい。そういうことだけは分かります。なにしろ壮絶な戦闘が硫黄島や沖縄の陸、海、空に展開され、本土には原爆2発を含むB29の爆弾が降りそそいでいたわけですから。しかし突然それはもう終わったと言われた。本土決戦も一億玉砕ももうないのだと言われた。耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍んで、ポツダム宣言を受諾したのだと。 ◇日本人はこれを受け入れた。恐らく理解しがたいままに強引に噛み砕いて飲み下した。しかしそのことによって戦後の日本は引き裂かれたのだと思います。少なくとも吉田喜重が『秋津温泉』で描き出した戦後の日本という空間はそういう空間です。ひとつは周作がそこに属する軽薄才子たちの俗なる空間であり、もうひとつは新子が属する現実的には存在しえない聖なる空間です。実際にはこの両空間は相互的で、ときどき入れ替わったりもする。恐らくそれは戦後に生きる私たち各人にも言えます。だがそうはならないこともある。この映画の新子のケースがそうなのです。だからこそ私たちはこの映画に震撼させられるわけです。新子が言う意味での「生きること」は、上手に世渡りすることでも、動物のように生存することでもないのですから。「戦後は終わった」と言われたのは昭和31年ですが、ここに言う意味での戦後は終わっておりません。昭和20年8月15日は隠されつつ現前しています。映画『秋津温泉』が告げているのはそういうことです。 ◇最後に新子のナルシシズムについて少し触れておきます。フロイトは「ナルシシズム入門」に次のように書いています。「特に美女の場合には、発達にともなって自己満足が発生し、対象選択の自由が社会的に歪められていることの償いをするのである。このような女性は、厳密な意味では自分だけを愛する」(フロイト/中山元訳『エロス論集』ちくま学芸文庫P.255)と。ここでは「美女の場合」と言われていますが、美男の場合でも、才能ある人間の場合でも、想像力に富む人間の場合でも、ほとんど同じことが言えるでしょう。とにかくこの定義からすれば『麦秋』の紀子がナルシストの資格を十二分に備えていることは明らかです。では新子の場合はどうか?彼女は「間違って」周作を愛したのか?そうではないと思います。彼女は「生きること」に忠実であり過ぎただけです。言い換えれば8月15日の巫女か天使のような存在になってしまった。上のフロイトの言葉の最後を「厳密な意味では生きることだけを愛する」にすると、新子のナルシシズムの姿が見えてくるはずです。そういう意味でも新子の運命は私たち自身の運命にほかならないと言えます。 |
 ◇前回の最後のところで予告したように、今回は吉田喜重の傑作メロドラマ映画「秋津温泉」で行きます。古書店の「おすすめ」で映画をとり上げるというのもなんだかへんですが、お許しを。「秋津温泉」は1962年の映画ですから、まあ古書みたいなものです。それに、優れた映画は文学や哲学の古典を「読む」ようにみなければならない場合があります。この「秋津温泉」もそのような読みを要請している映画と言えます。ただし、この「秋津温泉」も当店の在庫にはありません。ご了承ください。
◇前回の最後のところで予告したように、今回は吉田喜重の傑作メロドラマ映画「秋津温泉」で行きます。古書店の「おすすめ」で映画をとり上げるというのもなんだかへんですが、お許しを。「秋津温泉」は1962年の映画ですから、まあ古書みたいなものです。それに、優れた映画は文学や哲学の古典を「読む」ようにみなければならない場合があります。この「秋津温泉」もそのような読みを要請している映画と言えます。ただし、この「秋津温泉」も当店の在庫にはありません。ご了承ください。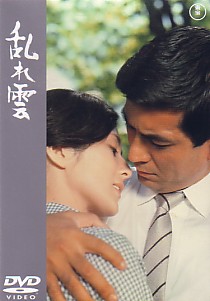 ◇最近の「今週のおすすめ」は当店の目録にないものが続いておりますが、今回も同様です。しかも前々回に続いて映画の話。とはいっても、今回は小津映画でも東映仁侠映画でもありません。最近見直して強い感銘を受けた成瀬巳喜男の遺作「乱れ雲」をとり上げてみたいと思います。この映画のストーリーは、内田樹の最近のブログのタイトル「一人では生きられないので死んで貰います」をもじっていうと、「二人が一緒になることを運命が許さないので別れて貰います」ということができそうです。
◇最近の「今週のおすすめ」は当店の目録にないものが続いておりますが、今回も同様です。しかも前々回に続いて映画の話。とはいっても、今回は小津映画でも東映仁侠映画でもありません。最近見直して強い感銘を受けた成瀬巳喜男の遺作「乱れ雲」をとり上げてみたいと思います。この映画のストーリーは、内田樹の最近のブログのタイトル「一人では生きられないので死んで貰います」をもじっていうと、「二人が一緒になることを運命が許さないので別れて貰います」ということができそうです。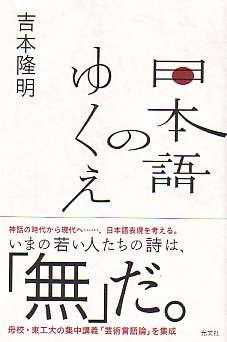 ◇「今週のおすすめ」の5回目は「吉本隆明本へのお誘い」(2007/09/25)というものでしたが、今回はその続編あるいは応用編といっていいかもしれません。「吉本隆明本へのお誘い」と違うのは、今回取り上げる『日本語のゆくえ』(光文社)は当店にはまだ在庫がないことです。ちなみにこの本の発行日は2008年1月30日。新刊書店では現在取り扱い中のはずですから、そちらでおもとめください。
◇「今週のおすすめ」の5回目は「吉本隆明本へのお誘い」(2007/09/25)というものでしたが、今回はその続編あるいは応用編といっていいかもしれません。「吉本隆明本へのお誘い」と違うのは、今回取り上げる『日本語のゆくえ』(光文社)は当店にはまだ在庫がないことです。ちなみにこの本の発行日は2008年1月30日。新刊書店では現在取り扱い中のはずですから、そちらでおもとめください。 ◇クラシックの中古CD全50点、それにポップス/ロックの中古CD全60点が新着なりました。目玉は多々あります。というか目玉でないようなものはひとつもないといったほうが正確かもしれません。とはいいましても何からご紹介しようかと考えると、やっぱりヤーラ・タールとアンドレアス・グロートホイゼンによるシューベルトの4手連弾曲から始めたいと思います。全部で4点(枚数にして7枚)ありますし。
◇クラシックの中古CD全50点、それにポップス/ロックの中古CD全60点が新着なりました。目玉は多々あります。というか目玉でないようなものはひとつもないといったほうが正確かもしれません。とはいいましても何からご紹介しようかと考えると、やっぱりヤーラ・タールとアンドレアス・グロートホイゼンによるシューベルトの4手連弾曲から始めたいと思います。全部で4点(枚数にして7枚)ありますし。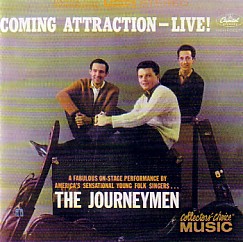 PPM(全5点)などがあります。
PPM(全5点)などがあります。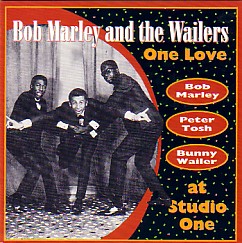 ◇レゲエの中古CD、ヒップホップの中古CD、それに映画の中古DVDが新着なりました。レゲエとヒップホップは当店としては初の新着となります。ですから少しコメントさせていただきます。
◇レゲエの中古CD、ヒップホップの中古CD、それに映画の中古DVDが新着なりました。レゲエとヒップホップは当店としては初の新着となります。ですから少しコメントさせていただきます。