| 今週のおすすめ〔28〕 |
◇ボッケリーニの音楽へのお誘い (2008/06/26)  ◇ご存知の方はご存知かと思いますが、当店の目録にはボッケリーニのCDがかなりあります。いま調べてみましたら、全部で21点あって、そのうち3点が売切れになっております。これは「パフォーマンス」という意味では必ずしも良いとは言えません。そういうこともありまして、今回はボッケリーニの音楽とCDを紹介させていただくことにしました。 ◇ご存知の方はご存知かと思いますが、当店の目録にはボッケリーニのCDがかなりあります。いま調べてみましたら、全部で21点あって、そのうち3点が売切れになっております。これは「パフォーマンス」という意味では必ずしも良いとは言えません。そういうこともありまして、今回はボッケリーニの音楽とCDを紹介させていただくことにしました。◇まず基本的なことからいきますと、ルイジ・ボッケリーニはイタリアの作曲家兼チェロの名手で、生年は1743年、没年は1805年です。ということは、パパ・ハイドンより11年、ヨハン・クリスティアン・バッハより8年後輩で、モーツァルトより13年、ベートーヴェンより27年、シューベルトより54年先輩ということになります。 ◇シューベルトより54年も先輩というのは意外です。なぜかと言いますと、ボッケリーニの音楽は、ハイドンはもとより、モーツァルトやベートーヴェンよりも更にロマンティックに聴こえるからです。ただしボッケリーニのロマンティシズムは、シューベルトのそれとは少し違います。ボッケリーニの場合はロマンティックというよりエロティックと言った方がいいのかもしれません。 ◇こう言ってしまうといきなり核心に入ることになりますが、シューベルト、シューマン、ブラームスのロマンティシズムと言ったって、エロス的なものとは無縁ではありませんから、ボッケリーニの音楽の先進性と独創性はある程度ご理解いただけることと思います。例えば喜多尾道冬氏はボッケリーニのある弦楽三重奏曲のレコードに触れて、「全体にあだっぽい女を愛撫するような官能的な歓喜に満ち、こ惑的な脂粉の匂いさえ漂ってくるほどだ」と述べています(『クラシック名盤大全・室内楽篇』音楽之友社、1999)。 ◇前置きはこれぐらいにしてCDを紹介させていただきます。弦楽三重奏曲からいくのがいいと思います。CDはFlieder-Trioによるボッケリーニ:弦楽三重奏曲集Op.14です(当店目録番号CC3274)。編成はヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ。ハイドンの弦楽四重奏曲「ひばり」をもう一歩ロマンティックにしたようなOp.14-1の導入部に魅せられます。1772年の作のようですが、上向音形、下向音形の味わいがウィーン古典派のそれとはひと味違います。第二楽章アダージョ・アッサイはそのままメロドラマ映画の主題曲に使えそうです。そういうものが全部で6曲収められたCDで、Flieder-Trio(男二人+女)の演奏も充分に魅力的と言えます。 ◇次は弦楽五重奏曲です。まずはファビオ・ビオンディ(vn)をフィーチャーしたエウローパ・ガランテによるボッケリーニ:弦楽五重奏曲集(Op.45-4他全3曲)です(目録番号CC3258)。このCDの3曲目には「鳥小屋」と呼ばれるOp.11-6の弦楽五重奏曲が収録されていますが、曲想からすると「鳥小屋」というより「鳥たちの楽園」と言った方がよさそうです。ボッケリーニによる田園の音楽とでもいいますか。ヴァイオリンのビオンディとチプリアーニが実に楽しい演奏を聴かせてくれます。とは言っても、ボッケリーニの中心ジャンルである弦楽五重奏曲の真価を聴かせるのは、アンサンブル415による演奏(CC3069)かもしれません。 ◇続いてフォルテピアノとヴァイオリンのためのソナタにいきます。CDはフランコ・アンジェレーリ(fp)とエンリコ・ガッティ(vn)によるものです(CC3273)。これはもう最高と申し上げるしかありません。シューベルトの場合もそうですが、この曲種になると作曲家たちは古典派的なつくり方をするようです。いやモーツァルトやベートーヴェンがロマンティックなつくり方をすると言った方がいいのかもしれませんが、まさにこれは夢見る古典派のヴァイオリン・ソナタ集です。名手ガッティの素晴らしさは言うまでもありませんが、アンジェレーリのフォルテピアノの美しさも絶品です。これほど美しい音楽は滅多にありません。 ◇次はピアノ五重奏曲です。編成はフォルテピアノ、ヴァイオリンx2、ヴィオラ、チェロで、演奏はGalimathias Musicumによるものです(CC3270)。これも素晴らしい。ヴァイオリン・ソナタと同じく古典派的な音楽ですが、これも夢のような音楽です。ボッケリーニはがっちりした構成でつくった場合の方がイマジネーションが自由になるのかもしれません。不思議な作曲家です。このCDでもヴァイオリンを弾いているのはエンリコ・ガッティですから、演奏は文句ありません。上に引いた『クラシック名盤大全・室内楽篇』にも取り上げられていて、「どれを買うか迷ったらまず本ディスクを」と安田和信氏が書いています。ただし、アンドレアス・シュタイアーがお好きという方には彼がフォルテピアノを弾いているCD(CC1051)をおすすめします。 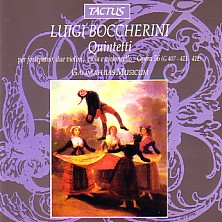 ◇目録をご覧いただければお分かりのように、ご紹介したいボッケリーニのCDはほかにもいろいろあります。ビルスマによる3点(CC0575、CC1049、CC1050)、弦楽四重奏曲3点(CC3070、CC3071、CC3072)、フルート五重奏曲(CC3067)、弦楽六重奏曲(CC1053)、ヴァイオリン二重奏(CC3271)、ホグウッドほかの交響曲2点(CC1048、CC1052)、更にはハイドンとカップリングされたヨーヨー・マのチェロ協奏曲(CC0187)もあります。 ◇目録をご覧いただければお分かりのように、ご紹介したいボッケリーニのCDはほかにもいろいろあります。ビルスマによる3点(CC0575、CC1049、CC1050)、弦楽四重奏曲3点(CC3070、CC3071、CC3072)、フルート五重奏曲(CC3067)、弦楽六重奏曲(CC1053)、ヴァイオリン二重奏(CC3271)、ホグウッドほかの交響曲2点(CC1048、CC1052)、更にはハイドンとカップリングされたヨーヨー・マのチェロ協奏曲(CC0187)もあります。◇このなかでは弦楽四重奏曲をおすすめしたいのですが、どなたにもおすすめできるということでは、ペペ・ロメロがギターを弾いているギター五重奏曲集でしょう(CC3159)。オーセンティックでしかも趣味的なセレナーデです。「ファンダンゴ」や「マドリードの帰営ラッパ」も入っています。とにかくボッケリーニの音楽には謎と楽しさがいっぱいです。ボッケリーニにとっては楽器の響きこそが謎に満ちた「他者」だったのかもしれません。 |
 ◇ひさしぶりに音楽の話です。まずメンデルスゾーンからいきます。なぜメンデルスゾーンかというと、これは前々回、前回の話のつながりになります。吉村公三郎の映画『暖流』にメンデルスゾーンの「春の歌」が出てくるのです。それも、およそピアノなどとは縁がなさそうに見える佐分利信が立ったまま「春の歌」の出だしのところを弾く場面があるのです。
◇ひさしぶりに音楽の話です。まずメンデルスゾーンからいきます。なぜメンデルスゾーンかというと、これは前々回、前回の話のつながりになります。吉村公三郎の映画『暖流』にメンデルスゾーンの「春の歌」が出てくるのです。それも、およそピアノなどとは縁がなさそうに見える佐分利信が立ったまま「春の歌」の出だしのところを弾く場面があるのです。 個々の音にというより、テンポや楽想の変わり目のようなところにです。とにかく聴いてみてください。ただし当店の在庫は1点きりです。ご了承ください。
個々の音にというより、テンポや楽想の変わり目のようなところにです。とにかく聴いてみてください。ただし当店の在庫は1点きりです。ご了承ください。 ◇今回は前回の続きです。この映画のドラマの骨格については前回おおまかに述べたつもりですが、映画のつくりについてはほとんど述べておりません。しかし言うまでもなく映画はドラマに還元されるものではありません。もしそうであるなら、映画をみる愉しみはかなり矮小なものになってしまいます。極端に言えば、あらすじと解説を読めば済むということになってしまいます。しかし映画には映画特有の表現手法や表現領域があります。今回は映画『暖流』に即してそれらについて考えてみたいと思います。
◇今回は前回の続きです。この映画のドラマの骨格については前回おおまかに述べたつもりですが、映画のつくりについてはほとんど述べておりません。しかし言うまでもなく映画はドラマに還元されるものではありません。もしそうであるなら、映画をみる愉しみはかなり矮小なものになってしまいます。極端に言えば、あらすじと解説を読めば済むということになってしまいます。しかし映画には映画特有の表現手法や表現領域があります。今回は映画『暖流』に即してそれらについて考えてみたいと思います。